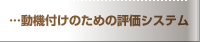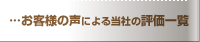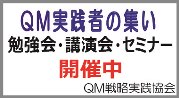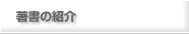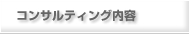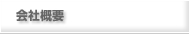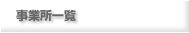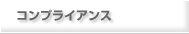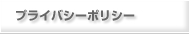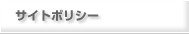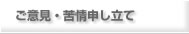QMSレポート@エヌケイエス株式会社 NKS 「ISOの品質マネジメントで、品質管理のPDCAを廻す」
当社のQMSの考え方とその流れをご紹介いたします
No.124 仕組みで仕事をするとは…
●2013年10月24日
■ 当社の校正業務HPで「仕組みにない仕事をさせ、失敗させてしまい
ました」という、先日起きたトラブルとその改善策を紹介している。
詳しくはコチラをご覧ください↓↓↓
校正業務のNKS@業務に活えるメルマガ情報 校正への工夫№74
【トラブルの概要】
①長期間にわたる作業で、お客様から「次回は模擬入力作業もお願
いするかも知れない」と聞いていた。
②当日模擬入力の話がやっぱり出たが、「もしも」のための標準器
を用意していたので、二つ返事で引き受けた。
③しかし、校正仕様も作業の準備状態も十分に確認せず安易にいじ
ったため、入力値の間違えにも気づかずに計測器の値を狂わせ
た。
上記の概要は、かなり私目線で纏めている。「キチッと確認もせずに勝
手に動くからこんな事になるんだって」と、トラブルの一報を受けた時
から「やった人の問題」と決めつけていた。
■ 最近の当社で起きているトラブルはこの手の「(勝手にやった)人の運
用の問題」が多い。
正直、技術や仕組みの問題なら手の打ちようがあるのだが、どんなにし
っかりとした仕組みを構築したとしても、やる人がやらなければ元も子
もない。「人の運用の問題」が一番厄介なのだ。
■ とは言うものの、トラブルを出し、お客様にも迷惑を掛けているのだか
ら、二度と発生させないための改善策をとらなければならない。
改めて事実から原因追究をしていく中で、「勝手にやった人の問題」と
いう固定観念に囚われすぎている私には思いつきもしないトップの意
見があった。
「現場で急遽依頼された仕事の仕様を確立もしないで受けてしまう
ような‘仕組み’の欠陥じゃないか。」
初めは「えー!?」と思ったが、これが自分だったら…「お客様に頼まれ
た」「何とかしてあげたい」「依頼の内容は経験がある」「やって大丈
夫だろう」…依頼内容にもよるが、このような発想になっただろう。
誰よりも仕組みに厳格と自負している私が思うくらいだから、他の社員
も同じだろう。
つまり…この程度の判断で仕事が進められてしまうような仕組みだっ
たということ。
「この程度」を止め「確立→判断」で仕事を進める仕組みを構築すれば
良いんだ!と気づいた。
■ そして打った手が『現場追加用の個別校正仕様書』(下図参照)で、現
場で急遽依頼されたお客様の要望を当該ドキュメントで聞き取り、対応
可否を「手順」「力量」「トレーサビリティ」の3つの側面から判断す
る。
これによって、個人の「要望聞き取り能力」や「対応可否判断力」に任
せっきりになることなく、会社として「社員を迷わせない、誰もが同じ
ことが出来る」基準が出来た。
初めは「こんなことまで仕組み~?」と思ったが、構築するとなるほど
と思えるし、社員の安心した表情が想像出来た。
仕組みで仕事をするって、こういう事なんだなぁ…とまたまた実感。
△ No.125 「無事故宣言」する人・しない人、それぞれのハンドルを握る想い
▽ No.123 QMS実現のキーワードは「目的・意味」