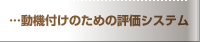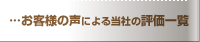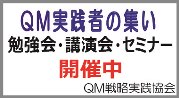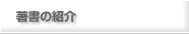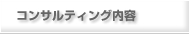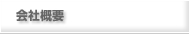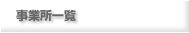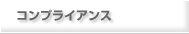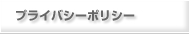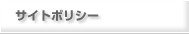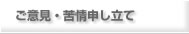QMSレポート@エヌケイエス株式会社 NKS 「ISOの品質マネジメントで、品質管理のPDCAを廻す」
当社のQMSの考え方とその流れをご紹介いたします
No.165 内部監査にかける熱い想い2 「これまでの内部監査を覆す」
●2016年3月17日
■ 前回は当社の本当につまらなかった内部監査の過去の姿をご紹介
しました。
今回はそれをどう「つまる」ものにしたかをご紹介したいと思いま
す。
■ 「もう社員だけの内部監査は諦めよう」と決心した社長が取った、
思い切った発想が「外部の見識者にお願いしよう!」でした。
「マネジメントの問題点の発見と質の向上」を目的とし、あくまでも
「社長の視点・代弁者」となれる外部の方(以下、外部監査員と呼
ぶ)に、内部監査のリーダーを委託しました。
従来は第三者審査のための1回/年でしたが、毎月1回計画的に、
事業所に行って現地で監査をする。
外部監査員はISO要求事項の用語を使わず、当社のQMSとその
活動の質を見てくれました。
■ するとだんだん効果が出てきた!
外部監査員だから、業務の遂行状況や仕組みのあり方を、客観的かつ
論理的に観察・指摘してくれる。
そこに社員同士ならありがちな情状酌量は無い。
だから指摘内容が運営やルール適用上などの、マネジメントの最も
基本的なことに触れるものばかり。
そして、当初は社員もまだ「従来の内部監査」の固定イメージが染み
付いていたため訝しがっていましたが、そこで話し合われることは
「記録に記入漏れがあるから不適合」とかではなく、
「どうやったら安心して、かつ確実に仕事が出来るか」が軸となってい
たため、徐々に「内部監査という場」を受け入れるようになってきたん
です。
また内部監査の状況は、TV会議システムで生中継もしています。
A事業所の監査に他事業所も自由に参加、発言出来るよう「開放的」
にした。
どんどん自分達の仕事について語られるようになり、拒否感・嫌悪
感が薄れ、次回を楽しみにするようになった。
まさしく「監査を受ける」から「討議をする場」に変わった…
ココが一番嬉しい効果だった。
■ このように「内部監査のやり方」を変えたことで、いろんな効果が
出てきました。
だけど監査そのものを変えただけでは「経営・運営」の質が上がる
訳ではないということに気づいた…
つまり、内部監査は「マネジメントの気づきの場」であって、仕事
・QMSに生かすためにはまだまだ工夫が必要!
■ ということで、次回は「内部監査をQMSに活かすための工夫」を
ご紹介したいと思います。
△ No.166 内部監査にかける熱い想い3 「不適合じゃない、改善の種だ!」
▽ No.164 内部監査にかける熱い想い1 「本当につまらなかった過去の姿」