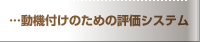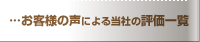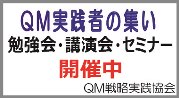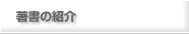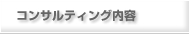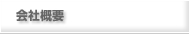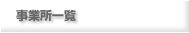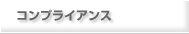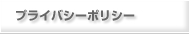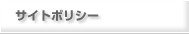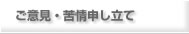QMSレポート@エヌケイエス株式会社 NKS 「ISOの品質マネジメントで、品質管理のPDCAを廻す」
当社のQMSの考え方とその流れをご紹介いたします
No.40 稼働率は下がった…でもそこから考えられるメリット
●2011年1月13日
■あけましておめでとうございます。
卯年は「飛躍の年」と云われます。
NKSも、QMSに基づいた上で更なる進化が出来るように、様々な問題・
改善の種に真っ向勝負する「チャレンジ精神」を大事にしたいきたいと
思っています。
■さて、昨年末「当社の標準単価を見直そう」という話題が挙がり、
・作業にどれだけ時間が掛かっているか
・市場価格
等を基に、現在検討を進めている。
その準備として社員の稼働状況を調べてみると、この1,2年稼働率が低く
なっていることに気づいた。
当初その要因は、一昨年のリーマンショックの影響で、大口業務が減った
から…と考えていた。
■しかし、トップから「本当にそうだろうか」という疑問が投げかけられた。
『稼働率が高いに超したことはないが、低くなった要因が何かによって
見方が変わってくる。
時間の使い方が生産的なのか、それとも非生産的なのか掴まないと
数字だけでは分からない。
例えば、ミーティングや勉強会をする時間が長くなれば、稼働率は
下がる。
しかしその反面、QMSが充実したり、業務に関わる知識が付く
というメリットが考えられる。』
■確かに、出先からは「3課ミーティングに多くの時間をとられている」と
いう声が有るし、内部監査でその運用状況も見ていて「時間を掛け、しっか
りやっているな」という印象が有る。
そのおかげで「QMSで仕事をする」業務の質も、運用者の意識レベルも
確実に向上している。
■これまで内部監査や日々の運用状況を見ていて、「QMSが定着しつつ
あるなぁ」と感じていたが、こういう稼働状況からも推測出来るんだ…
ただ、数字を数字として捉えるだけでなく、その数字から何を発想するか…
「発想は固執せず、広い視野を持て!」と教えてくれたテーマだ。